ライフサイクルの視点で環境影響を測る世界最大規模のインベントリデータベース
ライフサイクルの視点で環境影響を測る世界最大規模のインベントリデータベース
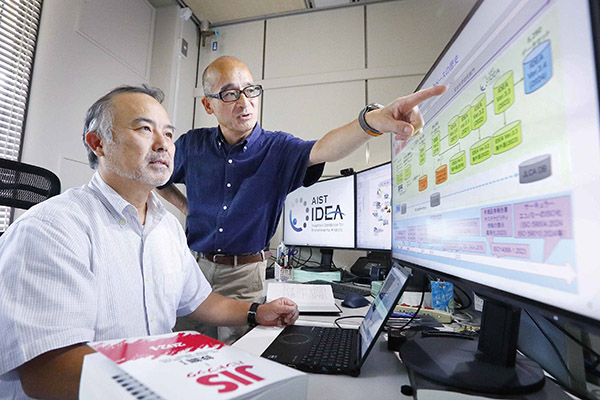
2025/05/14
ライフサイクルの視点で環境影響を測る世界最大規模のインベントリデータベース
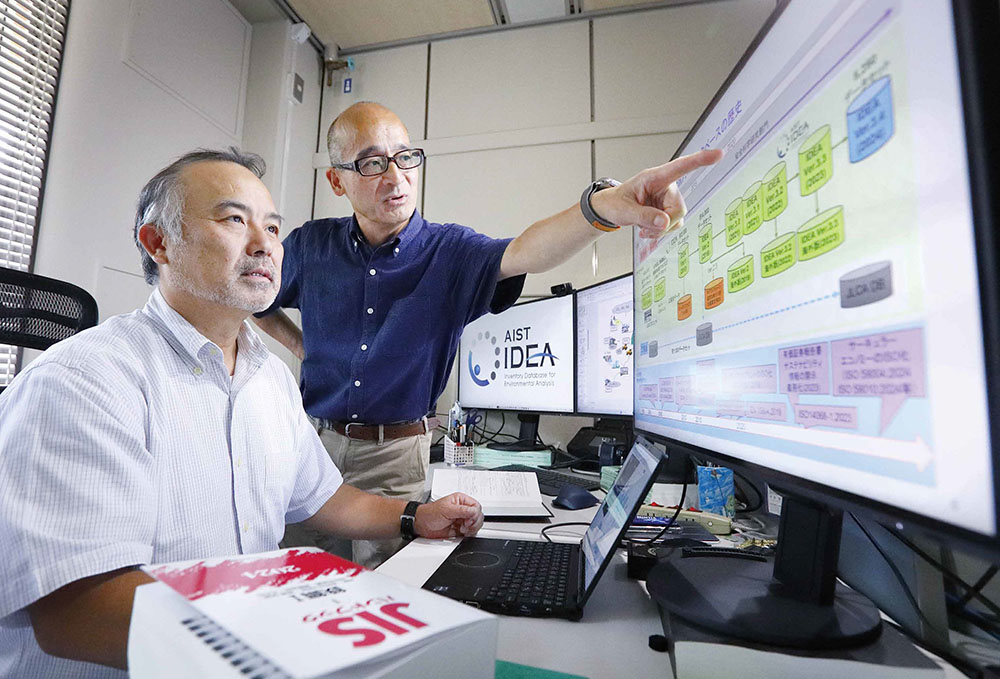
 ライフサイクルアセスメント(LCA)は、製品やサービスが環境に与える影響を「見える化」する手法です。企業がサプライチェーン全体の環境負荷を正しく評価するためには、製造に関わる直接的なデータだけでなく、資源採掘から廃棄・リサイクルに至るバックグラウンドデータが必要です。産総研ではそれらを網羅したインベントリデータベースAIST-IDEA (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology ‒ Inventory Database for Environmental Analysis。以下、「IDEA」)を開発。持続可能な社会の実現に貢献しています。
ライフサイクルアセスメント(LCA)は、製品やサービスが環境に与える影響を「見える化」する手法です。企業がサプライチェーン全体の環境負荷を正しく評価するためには、製造に関わる直接的なデータだけでなく、資源採掘から廃棄・リサイクルに至るバックグラウンドデータが必要です。産総研ではそれらを網羅したインベントリデータベースAIST-IDEA (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology ‒ Inventory Database for Environmental Analysis。以下、「IDEA」)を開発。持続可能な社会の実現に貢献しています。
日本のあらゆる産業を網羅しているからユーザーの求めるデータが得られる
気候変動をはじめとするさまざまな地球環境問題に対応するため、LCAの活用が企業に求められています。しかし、「作る」「使う」「捨てる」という各ステージの環境負荷を定量化するには、例えば購入した原材料を生産するのにかかったエネルギーまで追いかけなければならず、企業が自前でデータをそろえるのは現実的ではありません。そこで信頼性のある評価インフラを提供するため、産総研が開発したのがIDEAです。
2010年にIDEA Ver.1(3,000データセット)をリリースし、その後定期的に更新と拡張を重ね、今年4月にはIDEA Ver.3.4*1(5,250データセット)をリリースしました。
世界最大規模を誇るデータベースであるIDEA。その特徴である網羅性について、IDEAラボのラボ長も務める田原聖隆は次のように語ります。
「国の統計をベースに農業、工業、サービス業と日本の産業をすべて網羅し、5,250のデータセットを、日本標準産業分類をもとにした分類コードで整理しています。例えば食料品製造業(中分類)の下に畜産食料品製造業(小分類)を置き、さらに乳製品(細分類)、チーズ(細々分類)と階層構造にしているため、すべての製品が必ずどこかに当てはまり、ユーザーが求めるデータを得ることができます。IDEAの網羅性は世界的にみてもオリジナリティが高いものの、データの品ぞろえは総合スーパーマーケットではなくまだ小さな商店レベル。今後も多くの企業に使っていただきながら、アップデートをしていく必要があります」
 IDEAラボのメンバーたち。IDEAは多くの人の力を結集して作り上げられている
IDEAラボのメンバーたち。IDEAは多くの人の力を結集して作り上げられている
18領域におよぶ多様な影響領域と透明性のある単位プロセスデータ
続けて、IDEAの開発指針やデータ作成のポイントについて田原に聞きました。
「今は世界的に気候変動問題が注目されており、LCAは二酸化炭素(CO2)や温室効果ガス(Greenhouse Gas:GHG)の排出量をみるものと思われがちですが、IDEAはより広範囲にカバーしているのが特徴です。評価可能な影響領域は、酸性化、資源枯渇、有害化学物質の発がん性まで、全部で18領域におよびます」
また、単位プロセスデータの引用先やデータ作成方法を可能な限り公開することで、透明性を確保しています。単位プロセスデータとは、例えば製品をつくるとき、どういう材料やエネルギーを投入し、どんな物質が出てくるのか、ものの出入力データのことです。「企業は、製造法や各原材料の使用量など機密が多く、データを教えてもらうことはなかなかできません。そのため、エネルギー統計や化学物質排出移動量届出制度(PRTR制度)などの情報を頼りに、単位プロセスデータを推計します。そのとき、同じ製品でもさまざまな製法があるので、代表的、平均的なところを狙い、ある程度は見切ってデータを作成します。そこに私たちのテクニックとノウハウがあります」と田原は話します。
国際協調と社会ニーズを反映して大幅にデータを更新したVer.3.4
世界を見渡すと、インベントリデータベースを整備している国は少ないのが現状です。そうした中、国連のLCA国際データベース協調枠組み(GLAD)が、世界三大データベースのフォーマットをそろえ、相互に使えるようにしようと取り組んでいます。IDEA Ver.3.4は、そうした国際的な流れや社会ニーズを反映した更新がなされています。
また、国際的な規格やガイドラインでは、多様な要求事項があります。例えば、土地利用に関するGHG排出量の定量化です。森林を切り開くような人為的な土地利用の変化が、気候変動にどのような影響を与えるか、GHG排出量を定量化できるように大幅に更新して対応しました。次に、生物起因のCO2の扱いです。光合成により吸収したCO2と、バイオマスの燃焼などによるCO2の排出のバランスが取れているときは吸収も排出も0としてカウントする方が楽です。しかし、バイオマス製品のCO2固定量をきちんとカウントしたいという要望が増えているため、光合成で吸収したCO2はマイナスの排出量として固定量で表し、バイオマス製品などの燃焼時には、バイオマス由来の排出量を計上する取り扱いも必要になっています。すべてに対応することはできませんでしたが、暫定的な措置として各製品に固定されているCO2の量を提供し、固定量の把握ができるようにしました。
より広く活用される評価ツールを目指し終わりのない開発に力を注ぐ
IDEAの活用と普及を進める「LCA活用推進コンソーシアム*2」の運営に携わる門奈哲也に、活動内容を聞きました。
「会員は右肩上がりに増え、昨年度末で約500会員を数えます。LCAに関して初心者の会員もいますので、IDEAを正しく効果的に活用してもらうため、使い方講習会、なんでも相談会、講演会などのサービスを提供しています」
今年4月以降は、開発は従来通り産総研が行いますが、AISolが販売の窓口となり、従来の販売会社3社とライセンス契約を結ぶ形となりました。IDEAはすべての産業に関わるデータベースであるため、より多くの企業に使ってもらえるような体制を整えていきます。
今後の展望について、田原は「世界は2050年のカーボンニュートラルを目指して動いていますが、その時に環境負荷がどれくらい抑えられているかをみることも重要です。また、アジアを中心に国際協調できるようなデータベースを整備したいという夢もあります。それに向けて、IDEAを時間的・空間的に拡張する研究を実施していきたいと考えています」と構想を語ります。
最後に、IDEAの社会実装を進めてどういう社会をつくりたいか、門奈に尋ねました。「例えばお店に並ぶ食品に、成分と並んでGHG排出量が表示され、消費者がそれを見て買いたいものを選ぶ。そういうふうに、さまざまな商品、車、家などを買う時の判断基準にIDEAの成果が使用され、生活している人が自分事として環境影響を考えられる社会になればと考えています」
インベントリデータベースの開発には終わりがなく、持続可能な社会の実現に貢献するため、産総研はこれからもIDEAのさらなるバージョンアップに取り組んでいきます。
本記事は2024年9月発行の「産総研レポート2024」より転載しています。
*1:LCIデータベースIDEAは2025年4月に最新版のVer.3.5がリリースされています。また、現在は産総研が100%出資した株式会社AIST Solutionsより提供されています。[参照元へ戻る]
*2:
LCA活用推進コンソーシアムは2025年3月に活動を終了しています。活動やサポートの内容については、2025年4月より株式会社AIST Solutionsに引き継がれています。
[参照元へ戻る]
安全科学研究部門
総括研究主幹
IDEAラボ
ラボ長
田原 聖隆
Tahara Kiyotaka
安全科学研究部門
総括研究主幹
門奈 哲也
MONNA Tetsuya