産総研の新しいオープンイノベーションのスタイル
産総研の新しいオープンイノベーションのスタイル

2016/11/30
産総研の新しいオープンイノベーションのスタイルオープンイノベーションラボラトリ
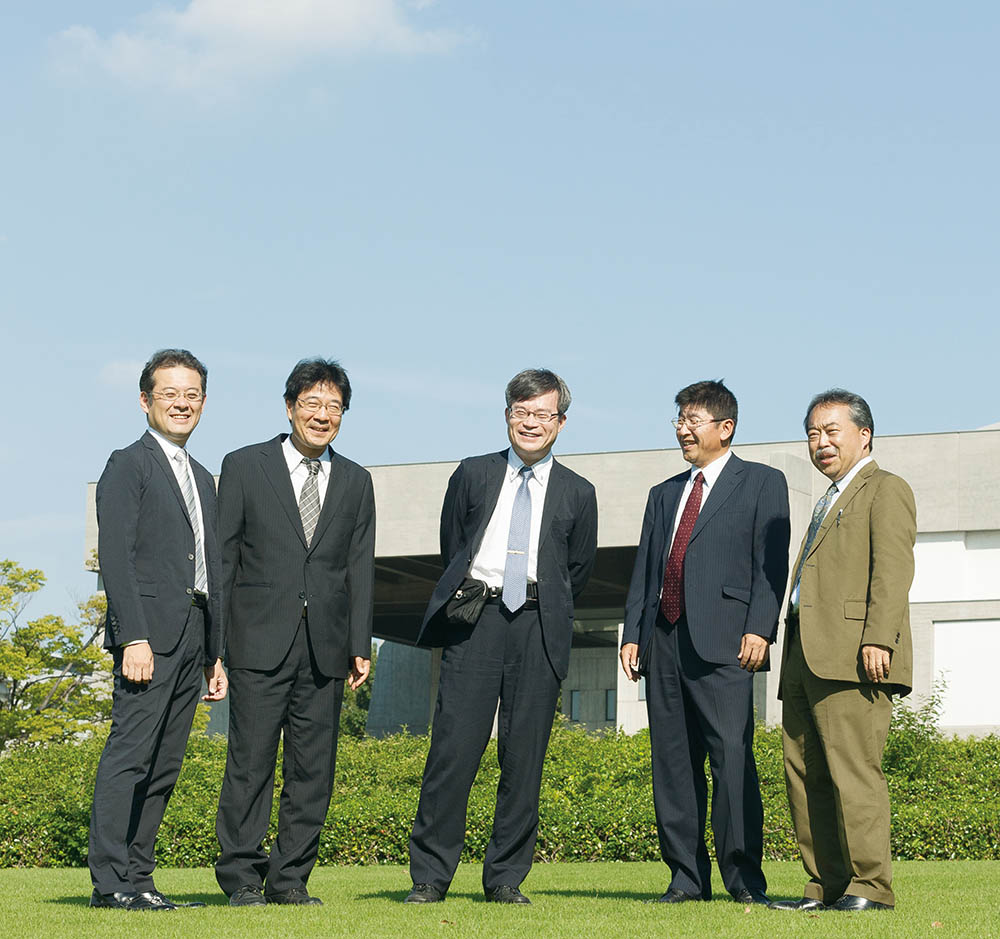
 ❶ さまざまな立場の専門家と連携でき、新しいモノを生み出す場になる。
❶ さまざまな立場の専門家と連携でき、新しいモノを生み出す場になる。
❷ 実践的研究を通じて、企業マインドをもつ博士人材を育成する。
❸ 大学と産総研の相乗効果で、基礎研究を迅速に実用化へつなげる。
産総研は現在、大学キャンパスの中に設置する産学官連携研究拠点「オープンイノベーションラボラトリ(OIL)」の整備に取り組んでいる。
基礎研究から応用研究、開発・実証までをシームレスに実施し、その相乗効果で最先端の研究開発をスピードアップすることが狙いだ。その第1号として、2016年4月、名古屋大学に、「産総研・名大 窒化物半導体先進デバイスオープンイノベーションラボラトリ(GaN-OIL)」を開設した。OIL設置の意義、OILへの期待や、今後の活動への意気込みについて、大学、企業、産総研それぞれからの視点で意見を交わした。

基礎研究から実用化へ新しいものを生み出す場に
安永産総研は2016年4月に、産学官連携研究拠点「オープンイノベーションラボラトリ(OIL)」の第1号を、窒化ガリウム(GaN)に関して革新的な基礎研究を行っている名古屋大学に設置しました。ノーベル物理学賞受賞者の天野先生をはじめ、第一線の研究者の方々と連携して窒化物半導体デバイスの研究開発を進めることで、基礎研究を迅速に実用化につなげていけると考えています。名古屋大学としては、この連携研究拠点にどのような期待をおもちですか。
天野OILの第1号として名古屋大学を選んでくださったことを誇りに思っています。この広報誌のタイトル通り、さまざまな面での「リンク」が生まれると期待しています。
大学は学部、学科に細かく分かれ、研究者の関心や交友範囲もどちらかというと専門分野に偏りがちです。それに対してOILは、産総研や企業など、さまざまな立場の専門家と「リンク」ができ、新しいモノを生み出す場になっていくと思います。
OILは同時に、大学と社会を「リンク」する場にもなるでしょう。大学の研究も、最終目標は社会に成果を還元していくことにあります。その意味でも基礎研究を実用化につなげるノウハウをもつ産総研との連携はありがたく、ぜひ、一緒に新しいモノを世の中に出していきたいと考えています。
安永清水さんは、産総研でGaNの研究に携わり、今回OILのラボ長に就任しました。産総研の立場からOIL設置をどのように受け止めていますか。
清水交流の中で新しいシーズやアイデアが生まれることは研究開発にとって大変重要です。OILは自動車や医療、IT分野などの産業、それも大企業からベンチャーまで、さまざまな立場の方と新しい課題に取り組むことができる場であり、産総研の使命である「橋渡し」の観点から絶好の機会だと考えています。実際、このような連携の場なら、ぜひ参加したい、という企業の方もいらっしゃいます。
大学にも企業にも役立つ産総研の「橋渡し」のノウハウ
安永クロスアポイントメント制度を利用して、宇治原先生には名古屋大学と産総研の両方に籍を置いて活動していただいています。
宇治原最近は大学にも社会への貢献が求められていますが、研究成果を世の中に出していくことは簡単ではありません。産総研の「橋渡し」のノウハウが、現在の大学の悩みを解決してくれると期待しています。
私は大学で、基礎研究だけでなく実装段階の橋渡し研究も行ってきましたが、一人の人間が一つの立場で両方に携わる効率の悪さを感じていました。しかし、今回クロスアポイントメント制度を活用したことで、基礎研究は大学で、橋渡し研究は産総研でと明確に立場を分けられ、改めて両方を自分のミッションとして位置付けることができました。これが同じような志をもつ研究者の見本になればよいと思っています。
安永この20年、日本経済の成長率が低い中で、東海地区は自動車産業をはじめ、新しいイノベーションを生み出しています。恩田さん、自動車部品メーカーご出身という立場から、OILへの期待をお聞かせください。
恩田私は、産総研とは長くシリコンカーバイド(SiC)の研究でお付き合いしてきました。産総研との共同研究は大学の研究と異なり出口が明確ですし、企業とは違うオープンスタンスをとる組織ということもあり、SiCの研究では非常によい成果を出すことができました。その産総研のOILが名古屋大学に設置されたことで、新しい価値を創り出す大きな可能性を感じています。
企業は大学の知見をすぐに使えないことが多いので、そこを上手に橋渡しする役割を担っていただきたいですね。そうすれば企業は事業化に向けて大学の技術を活用しやすくなります。そうやって地域の産業に技術を展開してくれるのはありがたいことです。
企業マインドを知ることは学生にとっても大きな価値
安永OILには基礎研究から実用化までのシームレスな研究開発のほかに、産業界で活躍できる博士人材を育成するという狙いもあります。産総研のリサーチアシスタント制度*1も活用し、若手の研究も応援したいと考えています。
天野学生は現場で鍛えられるものなので、産総研との連携はとてもよい経験になるでしょう。今まで大学だけではできなかったことにチャレンジしてほしいですね。OILでチャンスをつかみ、世界にはばたく人材が出ることを期待しています。
宇治原単に経済的な支援という意味であれば一般の奨学金と変わらず、大学が産総研と研究する意味は薄れてしまいます。ここで学生に期待するのは、企業などの現場に近いところで力を発揮してもらうことです。今の学生には高い能力がありますが、彼らの多くはその価値に気付いていません。リサーチアシスタント制度で学生を雇用することで、彼らのスキルや発想に対価が与えられれば、自分の能力には価値があると気付き、それを生かそうとするきっかけになるでしょう。ベンチャーを起業するような学生も増えるとよいですね。
清水学生には企業との共同研究に参加してもらい、企業のものの見方を学んでもらいたいです。最初から社会実装を目的にすることで、アイデアから実際にシステムをつくっていくときの課題も実感できるでしょう。それは、研究者として必ず役に立ちます。
恩田早い時期に企業と触れる機会をもち、事業化マインドを吸収してもらうメリットは大きいです。企業は製品化の部分を担当し、学生にはアイデアを技術に落とし込むことに取り組んでもらうとよい経験になるのではないでしょうか。
生き残れる技術の探索と研究開発のスピードアップ
安永GaN-OILがスタートしてまだ半年ですが、現在の課題や手応え、意気込みをお聞かせください。
清水橋渡しをしたとしても、市場に出せた技術のうち、実用化されるものもあれば、花開かずに終わるものもあるのが現実です。少しでも生き残る可能性の高いものを、企業と議論しながら探していくプロセスが重要だと考えています。
宇治原私は今までSiCの研究をしてきましたが、SiC研究の方法論をGaNにも活用できるところがあるように思えます。SiCの研究で得られた知見を生かすことで、GaNの研究開発はよりスピードアップするでしょう。機械学習の手法を導入するという発想も、学生たちから出ています。学生ならではの柔軟性を生かすことも、大学として貢献できることの一つですね。
異分野の集積こそ総合大学の価値
安永名古屋大学はノーベル賞受賞者だけではなく、オリンピック選手も輩出し、まさにuniversityだと感じます。人文系を含めた多様な分野の知的刺激を受けながら研究できることは、とても価値のあることだと思いますね。
天野総合大学であるuniversityの意義はまさに、さまざまな分野が一つの場に集まっているところにありますからね。
宇治原デザインにしても、「デザイン+工学=プロダクトデザイン」というように、単にくっつけることが融合ではありません。研究を深く理解するために、あるいは産業を効率化するためにデザインが必要だということに、異分野の人と日々接していると気付きます。研究論文のグラフも、書き方一つで理解の深まり方がまったく違い、デザイン系の人はそこをわかっていてとてもうまく進めてくれるわけです。
恩田東京でも大阪でもない、名古屋には独自の文化・雰囲気があります。名古屋大学にはこの周辺出身の学生が多く、互いに壁をつくらず、新しいことでも一緒に抵抗なく始められる校風につながっていると感じます。
安永本日は貴重なお話をありがとうございました。
産総研ではこれまで、名古屋大学のほかに東京大学、東北大学、早稲田大学にもOILを設置し、さまざまなテーマで連携研究を進めています。OILという新たな連携研究拠点を置くことで、これまで以上に産学官のネットワークを構築し、「橋渡し」につながる研究開発を推進します。また、これらOILへ企業からも参加いただき、連携したいと考えていますので、ご関心をおもちの皆さんは、ぜひ産総研にご連絡ください。

*1: 特に優れた大学院生を「産総研リサーチアシスタント」として雇用する制度。雇用された大学院生は、産総研が実施している社会ニーズの高い研究開発プロジェクトに参画するとともに、その研究成果を学位論文に活用できる。[参照元へ戻る]
産業技術総合研究所
理事
安永 裕幸
Yasunaga Yuko
名古屋大学
未来材料・システム研究所
未来エレクトロニクス集積研究センター
センター長 教授
産業技術総合研究所
桂冠フェロー
天野 浩
Amano Hiroshi
窒化物半導体先進デバイスオープンイノベーションラボラトリ
ラボ長
清水 三聡
Shimizu Mitsuaki
名古屋大学
未来材料・システム研究所
未来エレクトロニクス集積研究センター
教授
窒化物半導体先進デバイスオープンイノベーションラボラトリ
副ラボ長
宇治原 徹
Ujihara Toru
株式会社デンソー
基礎研究所
技師
(現在、名古屋大学 未来材料・システム研究所 出向中 特任教授)
恩田 正一
Onda Shoichi
産総研・名大窒化物半導体先進デバイスオープンイノベーションラボラトリ(GaN-OIL)