成果の「橋渡し」によるイノベーション創出が最大の使命
成果の「橋渡し」によるイノベーション創出が最大の使命

2015/07/31
成果の「橋渡し」によるイノベーション創出が最大の使命
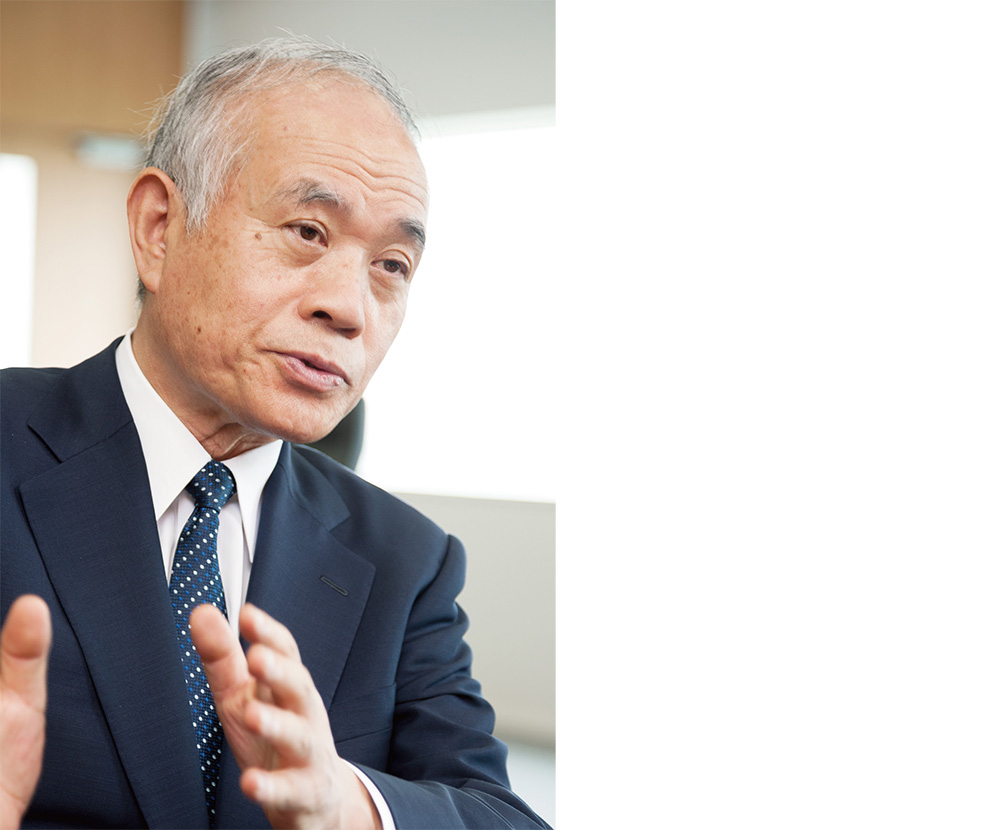 今年4月に第4期中長期計画をスタートさせ、同時に「国立研究開発法人」に指定された産総研。第4期中長期計画で定める産総研のミッションと、その達成に向けた施策、組織改編の意図、産総研の強みなどについて、中鉢理事長に聞いた。
今年4月に第4期中長期計画をスタートさせ、同時に「国立研究開発法人」に指定された産総研。第4期中長期計画で定める産総研のミッションと、その達成に向けた施策、組織改編の意図、産総研の強みなどについて、中鉢理事長に聞いた。
技術の橋渡しと目的基礎研究
──理事長就任以来、産総研の認知度を高めるために活動されてきた手応えはいかがですか。
中鉢2年前に民間企業から産総研に来ましたが、思っていた以上に産業界での認知度が低いと感じました。産総研には敷居が高いイメージがあり、それゆえに企業から気軽にアクセスしていただけなかったのではないでしょうか。その産総研のイメージを「敷居は低く、間口は広く、奥行きは深く」に変えていきたいと考えていました。
そこで、まずは最大のクライアントである産業界の方々、特にこれまで産総研とかかわりのなかった方々にも親しみをもっていただこうと、「AISTアカデメイア」という意見交換会を開催し、交流の機会を設けました。企業トップや有識者を講師に招き、2013年度から現在まで延べ30回開催し、これまでに500名を超える方々に参加していただきました。
おかげさまで産総研への理解が広がりつつあり、企業内でも多様な機会に産総研の名前がでるようになったと聞いています。企業からの問い合わせや共同研究、メディアへの露出度も確実に増えており、この2年の取り組みに、確かな手応えを感じています。
──公的研究機関である産総研の役割は、どのようなところにありますか。
中鉢国立研究開発法人となり、「研究成果の最大化」を目指すことがより明確化されました。そして産総研第4期のミッションは、技術的イノベーションの成果を産業界に「橋渡し」すること、イノベーションの基になる「目的基礎研究」を進めること、そして将来のイノベーションを担う「人材育成」です。これらについての社会的・経済的影響度を最大化することが重要ですが、公的研究機関としては特に、市場原理が必ずしも働いていない標準化や環境・地質などの領域についても、社会的影響を意識して取り組んでいく必要があると考えています。
産業界からわかりやすいように “看板を”かけ直す
──第4期の中核テーマを達成するための、主な施策をお聞かせください。
中鉢産業界から産総研の研究テーマを見やすくするため、研究組織を従来の6つの研究分野から7つの研究領域に再編しました。これまでは、ナノテクノロジー・材料・製造で1分野になっていましたが、これを「材料・化学」「エレクトロニクス・製造」の2領域に分けたことが最大の変更点です。
同時に、産業界の領域と産総研の領域ができるだけマッチするよう、産業カテゴリーに合わせて各領域の名称を変更しました。“一枚看板”にすることには議論もありましたが、そば屋がかつ丼を出していても「そばとかつ丼屋」とは書きませんよね。そのようにコアテクノロジーに絞り込んで看板が明示されている方が、産業界の方々が産総研に相談したいと考えたときにわかりやすいはずです。ドアにきちんと看板がかかっていることは、産業界から見るととても安心感があり、この施策が及ぼす効果は大きいと思います。
また、各領域には資金面、人材面で大幅に自主性を与えました。それぞれ掲げた目標の達成度は、次の4点についてKPI(重要業績評価指標)で確認・評価していきます。「橋渡し」については民間企業からの外部資金の提供額で、「目的基礎研究」は論文数で評価します。「人材育成」についてはアウトリーチ活動を目安にし、9月までにはこの数値目標設定を終了させます。もう一つ、「知的財産の利活用」についても定量的に定めています。
領域間融合と人材育成を促進
──イノベーション創出のためには領域間を融合させ、高いシナジー効果を上げることも重要だと思いますが、それに向けた取り組みは。
中鉢産総研は複数の領域をカバーできる研究の総合性を備え、多数のスペシャリストもいます。融合できる条件は整っており、これを活かさない手はありません。このため、7領域の実務代表者が研究戦略のテーマや技術移転の方法などについて具体的に議論する「研究戦略・イノベーション連携委員会」を設立しました。常に顔を合わせて話ができる場によって、これまで以上に融合が進むと期待しています。
──人材育成の取り組みについてはいかがですか。
中鉢各領域での人材面の自主性を高めると、産総研全体の人材流動性や他領域との融合性が落ち、また、人材評価が固定化する懸念があります。そのため、人事面のガバナンスの強化を目的にした「人事委員会」を発足させ、360°評価や人材交流を行っています。人材育成についてはクロスアポイントメント制度*1やリサーチアシスタント制度*2も設け、産学との交流をより進めていきます。
これらの委員会や制度については、昨年度より中長期計画を前倒しする形で導入しており、改革のスピードも上がってきています。
オール産総研で地域経済の活性化に貢献し、ナショナル・イノベーションシステムの中核を担う
──地域経済の活性化・地方創生も、日本経済にとって大変重要な課題ですが。
中鉢全国にある産総研の7つの地域センターにおいては、地域の特性を活かした研究をすることにさらに注力し、地域の企業に貢献していきます。その実現のために、地域センターの“看板”も再定義を行いました。例えば、北海道は「バイオものづくり」、東北は「化学ものづくり」、中部であれば「機能部材」など、1地域センターに1テーマ(関西のみ2テーマ)を与え、そのセンターのコアテクノロジーとして明示しています。
そして、地域の産業界との橋渡しや技術マーケティングの強化のために、地域のイノベーションコーディネータを任命、民間からも登用して質量の拡充に努めるとともに、都道府県の公設試験研究機関とも連携して、地域企業との協力関係強化に取り組んでいきます。
重要な点は、地域の技術ニーズに応える地域センターの背後には、オール産総研が控えているということ。それでカバーできないものはほかの公的研究機関、さらには海外の研究機関とも連携して、プレソリューションをできるだけ速やかに提供する体制をつくっています。この体制がきちんと機能すれば、これはまさに、国が構築を目指している「ナショナル・イノベーションシステム」の一部といえるのではないでしょうか。
──イノベーションを最大化するためには、どのようなことが必要ですか。
中鉢公的研究機関だけではなく、産学官に加えて金、すなわち金融も含めてうまくまわしていくということです。イノベーションにフォーカスするのは世界的潮流であり、日本も遅れをとってはいけません。この総力戦の中核として、産総研はとても大きな役割を担っていると自覚しています。
研究者の情熱と研究ポテンシャルを実用化につなげる
──産総研の強みは、どのような点だとお考えですか。
中鉢一言で言えば、研究に対する「情熱」です。研究者の研究への集中度はとても高く、仲間が触発し合う環境にも恵まれています。最終的にノーベル賞を受賞したいという夢をもつ研究者は少なくありませんが、産総研に来てみるとすでに優れた先輩がたくさんいて、「世界一になりたい」という夢は、まず「一人前になりたい」という夢に切り替わるようです。実は一人前になるまでが長いのですが、産総研ではその道のりを経て「第一人者」になった研究者が大勢います。「世界一」はその先に見えてくるものであり、それが見える環境にあるのが産総研です。そのため、研究者は誇りをもって研究できるのだと思います。
情熱あふれる研究者たちのポテンシャルの高い研究を、いかに実用化につなげていくか。これが現在の課題です。技術シーズは数多くあるのに、シーズとニーズのマッチングがなかなかうまく進んでいない。技術の橋渡しをするイノベーションコーディネータの養成が急務です。また、企業から産総研にアクセスするゲートウェイを増やすため、地方の公設試験研究機関などの研究機関、大学、そして金融機関とも連携しています。いずれは、さまざまな企業支援制度の中から適切な制度を紹介することができ、産総研ワンストップソリューションにつなげられるコンシェルジュのような人材も養成していきたいと考えています。
──今後、産総研と仕事をしたいと考えている方々にメッセージをお願いします。
中鉢産総研には現在約2600名の研究者(企業や大学からの研究者を含めると7000 ~ 8000人)がいますが、人生を賭けている研究が、生涯に一つでも二つでも実用化されて欲しいというのが彼らの願いです。科学者として生まれ、論文だけで認められるのでなく、皆、実社会の役に立ちたいのです。
新広報誌「産総研LINK」では、企業と産総研が連携していくヒントになるような情報とともに、どのような研究者がどんな研究をしているのか、そのストーリーを発信してまいります。ぜひ、彼らの熱い思いを受け止めてください。
グローバル競争の中で産総研は、日本企業によりオープンに使っていただける組織を目指します。企業内での研究の重なりを避けたり、規模感のある研究を行いたいときなど、産総研をこれまで以上に活用してください。自社の研究所がもう一つあるというぐらいの気持ちで気軽に声をかけ、使っていただければと思います。研究成果を実用化する道は厳しいと思いますが、産総研をパートナーとして、成功に至るまでのプロセスを共有し、ともに歩ませていただければと願っています。